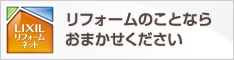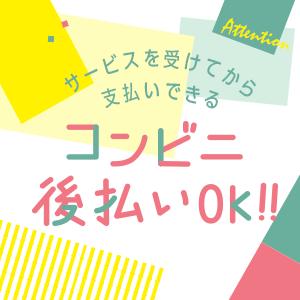水のコラム
香川県は水不足?ダムと用水路で支える節水型の街づくり【水道職人:プロ】

瀬戸内の温暖な気候と「うどん県」の愛称で知られる香川県ですが、年間降水量は全国平均の約6割程度しかないことをご存じでしょうか。
大きな河川も乏しく、ひとたび雨が続かないと水源はすぐに細ってしまいます。
それでも県民の暮らしや名物・讃岐うどんを支えているのが、吉野川から水を導く香川用水と各地のダム群、そして住民が培ってきた節水文化です。
この記事では、香川県の水不足についてご紹介しつつ、渇水に強いまちづくりやうどん文化との関わりについてなど、分かりやすくまとめてみました。
雨が少ない香川と慢性的な水不足の背景

「うどん県」と呼ばれる香川は、実は雨の少ない県としても有名です。
年間の降水量はおよそ1,150ミリメートル。
全国平均のおよそ6割しかなく、近県の徳島や高知と比べてもぐっと少なめです。
瀬戸内の空は晴れの日が多く、台風が来ても周囲の山々が雨雲をさえぎってしまうこともしばしば。
しかも、香川には大きな河川がなく、ダムを造れる深い谷も多くありません。
こうした要因から、ひとたび雨が続かない期間が続くと、ダムやため池の水位はみるみる下がり、取水制限がかかるのも珍しくありません。
1994年(平成6年)には、通称「高松砂漠」と呼ばれるほどの大渇水(だいかっすい)が起こり、給水車が街を回って水を配る光景がニュースで連日流れたほどです。
雨の少なさと水源の乏しさ。
この二つが重なる香川県では、いつの時代もどのようにして水を確保するか、が大きな課題となっています。
吉野川の水を運ぶ大動脈|早明浦ダムと香川用水

香川にとって「命の水道」と呼ばれるのが、徳島県の山あいにある早明浦(さめうら)ダムです。
四国を横切る大河・吉野川の上流に築かれたこのダムは、いわば巨大な貯水タンク。
ここから延びる「香川用水」という導水路が、約80キロもの距離を旅して香川県まで水を届けています。
高松市の水道水を例にすると、半分以上がこの香川用水に頼っている状況です。
農業用水も同じで、田んぼや畑を潤す大切な水源になっています。
雨が少ない香川にとって、県外から水を引くこの仕組みは、いわば「生命線」と言っても大げさではありません。
ただし、頼みの綱である早明浦ダムも、雨が極端に少ない年には水位が下がり、取水量を制限せざるをえなくなります。
大量の水を運んでくれる頼もしい存在ですが、それだけに頼りきりにはなれないのが現実です。
渇水に強いまちづくりと県民の節水文化

香川県は「雨が降らないのなら、降ったときに上手にためて大切に使う」という方針で、水不足対策を少しずつ積み重ねてきました。
ここでは、その取り組みと県民の身近な節水アイデアについていくつかご紹介します。
ため池|雨水利用のインフラ整備
県内には大小合わせて1万4,000ヵ所ものため池があります。
昔から農業用に使われてきましたが、近年は堤(つつみ)のかさ上げや耐震補強をして、より多く、より安全に水をためられるよう改良が進んでいます。
さらに公共施設や大型店では、屋根に降った雨をタンクにため、トイレの洗浄水や植栽の散水に回す「雨水利用」も広がっています。
家庭・事業所向けの節水設備と補助制度
高松市などでは、節水型トイレやシャワーヘッドに交換するとき、工事費の一部を助成する制度が整備されています。
お店や工場が雨水タンクや再生水配管を導入する場合も、補助が受けられるケースがあります。
助成があるならこの機会に…と設備を入れ替える家庭や事業所は年々増え、上水道の使用量はゆるやかに減少傾向にあるとのことです。
讃岐うどんを陰で支える水の力

香川といえば、やっぱり「讃岐うどん」。
コシのある麺をつくるには、小麦粉・塩・いりこだしに加え、たっぷりの水が欠かせません。
実は、香川用水で運ばれてくる吉野川の軟らかい水質が、うどんの滑らかなのどごしを支える大切な要素にもなっています。
うどん作りは、とにかく水量勝負
製麺所では、生地をこねたり、麺をゆでたり、冷水でしめたりと、1日で何百リットルもの水を使います。
水不足が深刻だった頃は、夜間断水を避けようと深夜まで仕込みを続けたり、給水車の水をタンクにためて何とか営業を維持したりと、涙ぐましい努力が続いたそうです。
用水と節水が、名物を守る
現在は香川用水のおかげで安定した水が確保でき、製麺ラインを止めずに済むようになりました。
それでも取水制限が出ると、飲食店や製麺所は一斉に「節水モード」に切り替えます。
麺の仕込み回数を減らしたり、ゆで湯の使い回し時間を長くしたり…名物うどんを守るため、現場の節水ノウハウは年々進化しています。
未来へつなげる「うどん県」の水インフラ

将来もおいしいうどんをゆで続けるためには、ダムや用水路だけでなく、再生水の活用や地下水の分散利用といった新しい選択肢も必要になるでしょう。
行政・事業者・家庭が一体となって水を大切にする文化を育てることで、「うどん県」の味と暮らしは、これからも守られていくはずです。
もちろんこういった問題は、何も香川県だけの話ではありません。
近年はどの地域でも、気候変動による渇水や豪雨の振れ幅が大きくなっています。
いざというとき困らないよう、雨水の活用や節水型設備の導入、日々の小さな節水習慣を積み重ねることは、私たち誰にとっても大切な備えと言えそうです。